エッセンス オブ フライ フィッシング & エッセイ オン フライ フィッシング vol.137「何やら見かけないヒラタ ―― ミチノクオビカゲロウ?」の棲む沢⑤ /竹田 正
2023年07月07日(金)
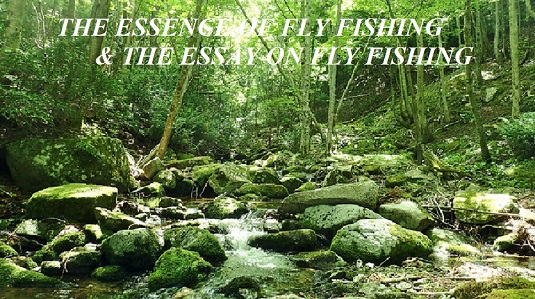
真夏の日差しを感じる6月。長く感じられた1年だった。心待ちにしていたこの季節が、ようやく廻り来たのである。
これまでの経験から、件の沢におけるオビカゲロウの羽化時期は、梅雨入りから夏至の頃に訪れると予測していた。2021年に新種として記載された「ミチノクオビカゲロウ」について、その知見をより深め確かなものとする良いタイミングである。昨年発見したオビカゲロウのニンフを、再度この目でしっかりと確かめたいという気持ちも強くあり、夏至に入った頃合いで、件の沢を再訪することにした。
過去の調査釣行において、2022年夏までに現認しているオビカゲロウは、メスのスピナーとダン共に1個体ずつ、ニンフは4個体のみである。言うなれば、たったのそれだけである。
そこで今回の調査は、昨年見つけたニンフの生息ポイントの他にも新たなポイントを見つけ出すことにある。より多くのニンフを採集することは勿論のこととして、新たに発見した生息ポイントを中心に周囲を探索することで、未だに現認していないオスのダンおよびスピナーを発見したいと考えていた。あわよくば、その繁殖行動まで観察することができれば、今回の調査は文句なしの調査結果となる。

 「前翅に帯紋が無い」ことから新種「ミチノクオビカゲロウ」として過去において現認したスピナーおよびダン ともにメス
「前翅に帯紋が無い」ことから新種「ミチノクオビカゲロウ」として過去において現認したスピナーおよびダン ともにメス
 昨年夏に現認したオビカゲロウのニンフ
昨年夏に現認したオビカゲロウのニンフスケジュールは今回も2日間。いつもの通り渓歩きを楽しみつつイワナを釣り、その調査と記録を行いながら、同時にミチノクオビカゲロウを探索することとした。毎度のことながら、やりたいことは盛り沢山であり、どっちつかずの行動には要注意なのである。
オビカゲロウを探索するポイントは、これまで通りに細流の落ち込みの飛沫帯や清水が湧きだしている岩盤などを想定していた。昨年の経験からニンフについては、石や岩の表面を塩梅が良く清水がさらさらと流れているところ、その周囲に張りついている落ち葉の裏を入念に探索することとした。
関連記事 「何やら見かけないヒラタ ―― ミチノクオビカゲロウ?」の棲む沢①~④
リンク vol.127 vol.128 vol.129 vol.130
釣行の1週間ほど前に、東北地方は梅雨入りとなったのだが、一時的にざっと雨が降ったものの降った雨はまるで夏のそれで、しとしとと降る梅雨らしい雨ではなかった。とは言え、そのお蔭でこれまで渇水していた沢の水量は平水に戻り、渓のコンディションは良好と思われた。
初日、朝の気温はやや肌寒く感じる13℃で、天候は穏やかに晴れ。森は良い雰囲気に包まれていた。渓筋に日が差し込み、景色が明るくなる頃を見計らって、森の奥へと踏み入った。

 緑光の空気に包まれた渓に響く音色。チュチュチュールルルル……、のびやかなメロディに乗って高らかで透き通った声が聞こえてきた。美しく可愛らしい囀りがせせらぎと調和し、幾度となく繰り返し響き渡る。生き生きとしている豊かな森と渓を歩き、それらを享受する麗しい時間。
緑光の空気に包まれた渓に響く音色。チュチュチュールルルル……、のびやかなメロディに乗って高らかで透き通った声が聞こえてきた。美しく可愛らしい囀りがせせらぎと調和し、幾度となく繰り返し響き渡る。生き生きとしている豊かな森と渓を歩き、それらを享受する麗しい時間。水温は11℃、イワナにとって適水温。ロッドを繋ぎフライを結ぶ。期待を込めてキャスティングを開始した。


 釣りを始めて直ぐにイワナから嬉しいご挨拶が来た。イワナたちはご機嫌な様子。小渓のイワナ釣り独特のリズム感を楽しむ。
釣りを始めて直ぐにイワナから嬉しいご挨拶が来た。イワナたちはご機嫌な様子。小渓のイワナ釣り独特のリズム感を楽しむ。
 フライを食べ損ねても、バレてしまっても、何度でもフライ目掛けて果敢にアタックしてくるイワナたち。皆、元気一杯!腹一杯に食べたがっている。まるでモリモリ良く食べる子供たちを見ているようで、なんだか嬉しい気分。
フライを食べ損ねても、バレてしまっても、何度でもフライ目掛けて果敢にアタックしてくるイワナたち。皆、元気一杯!腹一杯に食べたがっている。まるでモリモリ良く食べる子供たちを見ているようで、なんだか嬉しい気分。釣り開始から2~30分が経過、数尾のイワナを釣り上げた頃、ふたつ目の湧水を探索し始めた。周囲の状況も観察しながら、落ち葉をめくっていると、素早く流れ落ちる何かが見えた。それは見失ってしまったのだが、何やら怪しい感じがした。更に注意深く落ち葉をめくっていると、今度は横に動きながら流れ落ちていく何かがいた。
「何かいる、オビカゲロウに違いない」
シャーレとティッシュを取出し、採集の態勢を取った。そっと落ち葉をめくることを繰り返す。ニンフは横に動きつつ水に流されるであろうことを予想してティッシュを構えた。その結果、3個体のニンフを採集することができた。何かは見間違いではなかった。
一目見ただけでも分かる見覚えのあるその姿に、心が騒いだ。シャーレの中で動き回っているニンフは間違いなくオビカゲロウだった。





 結構な数のニンフを見つけたが、さしあたって採集したのは3個体。その内の1個体は、オビカゲロウに比べ少し丸くて黒く、異なる雰囲気を持っていた。画像を拡大して確認すると、腹部にヒラタカゲロウのようなエラが見当たらず、触覚や尾の配置はカワゲラのそれに見えた。やはり、それはオビカゲロウではなかった。思いもよらぬ意外な発見。特徴のある目と顔、それに体つきが可愛らしいノギカワゲラのニンフだった。
結構な数のニンフを見つけたが、さしあたって採集したのは3個体。その内の1個体は、オビカゲロウに比べ少し丸くて黒く、異なる雰囲気を持っていた。画像を拡大して確認すると、腹部にヒラタカゲロウのようなエラが見当たらず、触覚や尾の配置はカワゲラのそれに見えた。やはり、それはオビカゲロウではなかった。思いもよらぬ意外な発見。特徴のある目と顔、それに体つきが可愛らしいノギカワゲラのニンフだった。ノギカワゲラがオビカゲロウと同様な水辺環境に暮らす水生昆虫となれば、実際のところ意外でも何でもないのであるが、実物は今回が初見である。これもまた嬉しい出会い、宝探しである。
採集したオビカゲロウ2個体およびノギカワゲラ1個体と、これらが生息していた環境の写真。この湧水、実は過去にも探索していたのだが、その当時はうまく見つけることができなかったということになる。



 オビカゲロウニンフの再発見に心が躍った15分程、一通り周辺の探索も終えて釣りに復帰した。オビカゲロウのダンやスピナーを探しながら、釣れてきたイワナも観察・記録する。まだ痩せている感じはするが、薬指にはお腹のごろごろが感じられた。良く食べている。
オビカゲロウニンフの再発見に心が躍った15分程、一通り周辺の探索も終えて釣りに復帰した。オビカゲロウのダンやスピナーを探しながら、釣れてきたイワナも観察・記録する。まだ痩せている感じはするが、薬指にはお腹のごろごろが感じられた。良く食べている。





 釣りの合間に目に留まった湧き水を探索していると、今度はあっさりと見つけることができた。少しはオビカゲロウ探しに手馴れてきた感じである。
釣りの合間に目に留まった湧き水を探索していると、今度はあっさりと見つけることができた。少しはオビカゲロウ探しに手馴れてきた感じである。この場所では、湿潤しているところのみならず、岩の乾いた部分であっても、オビカゲロウが素早く移動していくのを目の当たりにした。これには正直言って驚いた。その動きはまるでカニのようだった。
この時まで、オビカゲロウはもっと水に接して生活しているものと考えていた。つまり、これまで探索していた環境よりも更に浅い水深、つまり「水中とは言えないところ」でも活動していたのである。水の流れをあまり感じないひたひたと濡れている程度から、じわっと湿っている程度の岩肌や苔の隙間、堆積した濡れ落ち葉の中など、思っていた以上に「陸」で生活しているように見受けられた。
ここではオビカゲロウ3個体、ノギカワゲラ1個体を採集し、岩肌で動き回るオビカゲロウニンフを写真に収めることができた。生態撮影も含め、今後更に工夫したいところ。



 白斑の大きさが揃っていて良い感じのイワナ。少し日が陰って来た。渓は暗くなるのが早い。16時を過ぎ、そろそろ退渓を考える時刻。
白斑の大きさが揃っていて良い感じのイワナ。少し日が陰って来た。渓は暗くなるのが早い。16時を過ぎ、そろそろ退渓を考える時刻。
この沢にも、アブドメンに白い帯のあるムネアカオオアリがいた。整列型白斑のイワナが棲む沢以外で見たのは初めてであるが、もしかすると森に棲むムネアカオオアリにとって、案外これが普通の事なのかも知れない。


 このイワナとの出会いで納竿。明るいうちに早めの退渓、帰着とし、翌日の遡行に備えた。
このイワナとの出会いで納竿。明るいうちに早めの退渓、帰着とし、翌日の遡行に備えた。幸いにもこの日は、数多くのオビカゲロウのニンフを見つけることができた。これまでの経験生かされてきたのか、探索するポイントの読みが定まり、採集にも慣れてきた感じで、これは良い傾向である。一方、残念ながらダンやスピナーの姿を見かけることは無かった。そもそもミチノクオビカゲロウの羽化期に関してはまだまだ経験不足であり、ざっくりと捉えることしかできていないのである。何かしらの手掛かりが欲しい。
翌朝、6時には起床しようと思っていたものの、暑くもなく寒くもない心地よい気温、鳥たちの囀りとせせらぎが気持ち良くて、つい二度寝をしてしまった。
まったりした気分のまま、がっちりと朝飯をとり身支度を済ませたのだが、ちょいと、のんびりし過ぎてしまった。森の奥へと踏み入り、渓に降りて釣りを始める頃には11時近くになってしまった。


 釣り開始早々の数投目にバシッと、ご挨拶。おはよう!いやいや、こんにちは!かな?今日もイワナのご機嫌は上々の様子だった。
釣り開始早々の数投目にバシッと、ご挨拶。おはよう!いやいや、こんにちは!かな?今日もイワナのご機嫌は上々の様子だった。


 この沢のイワナたちは所狭しとよく走り良く跳ぶ。心なしか頭は小さめで尖っているイワナが多いように感じた。
この沢のイワナたちは所狭しとよく走り良く跳ぶ。心なしか頭は小さめで尖っているイワナが多いように感じた。

 鈎掛かり直後にひとっ跳び。掬う直前にも、もうふた跳びする感じ。この時、結構バラシてしまうのだ。
鈎掛かり直後にひとっ跳び。掬う直前にも、もうふた跳びする感じ。この時、結構バラシてしまうのだ。

 小さな沢では、この規模で十分に大淵。体は小さいけれど、この淵の主。やや小さ目の白斑。
小さな沢では、この規模で十分に大淵。体は小さいけれど、この淵の主。やや小さ目の白斑。
 一段上を狙う。掛かったイワナは迎えに行くか、流れに乗せて下ろして取り込む。誘導に失敗して石などに当ててしまうと、思いのほか簡単にバレてしまう。
一段上を狙う。掛かったイワナは迎えに行くか、流れに乗せて下ろして取り込む。誘導に失敗して石などに当ててしまうと、思いのほか簡単にバレてしまう。
 この森のイワナたちには、心底惚れ惚れする。沢を詰めていくとなおの事、古よりこの沢に棲むイワナたちに脈々と引き継がれてきた「アメマスの血筋」が感じられるのだ……。
この森のイワナたちには、心底惚れ惚れする。沢を詰めていくとなおの事、古よりこの沢に棲むイワナたちに脈々と引き継がれてきた「アメマスの血筋」が感じられるのだ……。
 巨大なムネアカオオアリ、2cm位ある羽根つき。昼飯を食っているときに出くわした。撮影していると時折、ビリビリと激しく翅を震わせていた。
巨大なムネアカオオアリ、2cm位ある羽根つき。昼飯を食っているときに出くわした。撮影していると時折、ビリビリと激しく翅を震わせていた。 ニホンカワトンボ メス
ニホンカワトンボ メス全身に青竹色の銀粉をまとって光り輝く感じで、兎にも角にも美しい。
水飛沫を浴びながら無心に、木に何度もお尻の先をくっつけていた。どうやら産卵の真っ最中の様子。接近して写真を撮っていても全く動じることがなかった。
二ホンカワトンボはそこかしこで飛びまわっているのだけれど、依然としてオビカゲロウのダンとスピナーは見かけることがなかった。




 退渓後の帰着途中、昨年オビカゲロウのニンフを初めて現認した石に立ち寄った。当時、激しい雨が降る中、びしょ濡れになりながらオビカゲロウを発見したのだった。
退渓後の帰着途中、昨年オビカゲロウのニンフを初めて現認した石に立ち寄った。当時、激しい雨が降る中、びしょ濡れになりながらオビカゲロウを発見したのだった。さらさらと清水が流れるその周囲を探索すると、すぐにオビカゲロウを見つけることができた。流水に浸された小石の下にも見つけることができた。ここでは3個体を採集し、写真に記録した。特徴的な糸状エラと腹部背面体節正中線上に棘を持っている。
さて、今回の調査結果である。
件の沢ではこれまでに考えていた以上に、各所の湧水や細流にオビカゲロウが生息していることが分かってきた。しかしその一方で、2日間共にダンおよびスピナーを発見するには至らなかった。確実に羽化のタイミングを捉えるには、時間的に2日間ではやはり難しく、3~4週間程度に亘る張り込み調査の必要性を感じた。
採集したニンフの体長は最大で13mmを超え、最小で約6mm、10mm前後の個体が多数を占めた。大中小とその成長の具合には差があり興味深い。体長13mmを超える個体はその大きさから、今夏季に羽化する可能性が感じられるのだが、機会が得られれば再調査に向かいたいと思う。
オビカゲロウのニンフは、源流域の染み出すような細流やその飛沫帯という限られた環境に生息するが、今回は同様な環境に生息するとされるノギカワゲラのニンフも同時に採集された。なお、採集した水生昆虫は全て元の棲み処に帰した。
次に、釣れてきたイワナたちの白斑の状態を調べた。各々の個体でその大きさが揃い、落ち着いている印象を受ける個体が多数を占めた。特段に白斑に乱れを感じる個体や非常に薄く見えないほどの個体、稀に見かけることがある色素胞に問題がありそうな個体などは見受けられなかった。特に大きい白斑を持つ個体はいなかったものの、白斑の数が少なめの個体は若干見受けられ、整列型白斑の気配も感じられる個体もいた。まとめると、今回の調査では特段にこれといった個体には遭遇していない。イワナについても全て元の棲み処に帰した。
今回、ニンフの再発見と新たな生息ポイントも見つけることができた。しかしながら、オビカゲロウのダンとスピナーを見つけられなかった。さすがに繁殖行動の観察まで至るには、まだまだハードルが高そうである。こうなってくると、運の強さも必要なのかなと思う。今後は探索の範囲を今まで以上に大きく広げ、件の沢のみならず、他の沢でもオビカゲロウやノギカワゲラの生息状況を丹念に調べていく必要がありそうだ。
さて、こうして自然観察を続けていると、オビカゲロウが生息できる環境を包含する森とそこに流れる渓流は、とても貴重な存在であると強く感じるのである。
釣りは謎解き、ロマンである。宝探しの川旅は続く……。オビカゲロウとイワナ、豊かな森に感謝!ありがとう!
THE ESSENCE OF FLY FISHING & THE ESSAY ON FLY FISHING vol.137/ T.TAKEDA
← 前記事 vol.136 目次 次記事 vol.138 →









