エッセンス オブ フライ フィッシング & エッセイ オン フライ フィッシング vol.109 春の探し物/竹田 正
2020年05月29日(金)
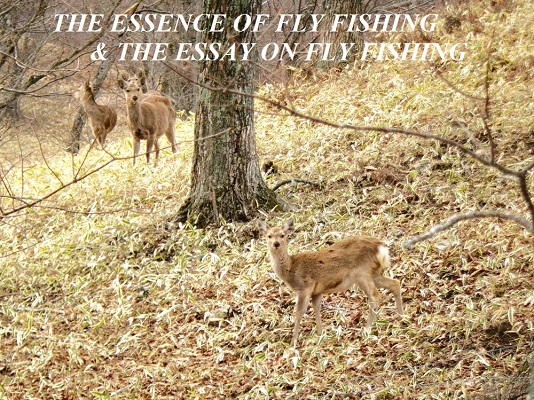
解禁当初は風に翻弄されることが多い。今シーズンもまさにその典型で、川へ出かけるたびに暴風に攻めたてられ、満足に釣りが出来ずにいた。なんだか、毎度ついてないよな~、と思いつつも、それでもめげることなく、毎週三陸の川へと通い続けた。先日の解禁釣行で出合った美しいヒカリの姿が心に焼きついていたからだった。「この春は久しぶりにヒカリを探しに、あちらこちらの流れを探索してみよう」とちょいとばかり本気になっていた。
大船渡から釜石にかけて、幾つもの単独小河川が太平洋へと流れ出している。いずれもその流程は短いが、リアス式海岸に特有と言える急峻な渓相が上流から下流まで続き、河口近くでも多くの渓流魚を育んでいる。夏には海水浴を楽しみながらも、ちょちょいとヤマメを釣ることもできたくらいなのだ。この豊かな環境を大切にしたいと常々思っているのである。
さて、3月下旬のコト。久しぶりに様子を見に行ってみるかなと、数ある川のうちのひとつを訪れてみた。さてさて、どこに入ろうか。日当たりが良くて、程良い流速の深瀬に淵が絡むような、ヒカリがせっせと餌を食べに来るような、そんなイメージを持ちながら、入渓場所を選んだ。

河口からわずか1kmほど上流の渓相。震災以降、度重なる災害からの復興を成し遂げ、見事に全線開通した三陸鉄道リアス線も間近を走っている。このような流れからヒカリ探しが始まった。
山から風が強く吹きおろし、ドライフライの釣り上がりなど到底無理な状況だった。9ft#3のロッドを取り出した。リーダーのティペットをばっさり切り詰め、ウェットフライを結んだ。ドロッパーに#12ブループロフェッサー、リードフライは♯16パートリッジ&オレンジという組み合わせとした。
いざ入渓、釣り下りを開始する。風にあおられて仕掛けが絡むことの無いよう、まずは丁寧なキャストを心がける。こちらの気配を気取られぬように、魚との距離感に気を付けつつ、ひとつひとつ流れの筋を探っていく。選んだポイントに問題は無いのか、フライは合っているのかなど、とかく釣り始めは疑問が付き纏うものであるが、幸いなことに程無くしてアタリがやってきた…。


だいぶヒカリになりつつある、嬉しい一尾。ドロッパーに食いついてきた。もしかして、活性は高めなのかな?絞られた流れが開く辺りでアタリが出た。大きめの石がごろごろで垂涎の流れ、そのフトコロ具合からまだ釣れてくるかと思いフライを流してみるけれど、釣れてきたのはこの一尾のみだった。


一段下って次を狙う。落ち込み付近から、一投ごと徐々に刻みながら、ラインとフライだけがステップダウンしていく。コントロールできる限り、自分は下らない。すると護岸脇の深瀬からぶるっとアタリが来た。二尾めはヤマメ。ギンは強めだったけれど、鰭の色付き具合がヒカリとは異なる。これもドロッパーを咥えていた。やはり今日は調子良いのかも!と期待させてくれるではないか。この流れも複数釣れてきて欲しいくらいの良い流れなのだが、結果このヤマメのみだった。


しかしもって厄介者の風。普段よりもひと手間もふた手間も多くなる。フライが絡み合っていないか確認しながらのキャストが続く。もやもやした流れを通り過ぎたフライに、またアタリがやってきた。今度はヒカリ。これもドロッパーを咥えていた。ブループロフェッサーが大人気である。
ふと、カゲロウのハッチに気付いた。カゲロウが流れから飛び出すやいなや、強風に吹き流されていく。
「そうか、そうだったのか。今羽化しているのはおそらくナミヒラタカゲロウ。それでドロッパーのブループロフェッサーなのか」一つの鍵を手に入れた気がした。よくよく観察してみると、散発ながらカゲロウが飛んでいくのが見えた。間違いなくチャンスが訪れている。
今しがた釣った流れの下手にフライを送り込んだ。流れは開き始めている。より強めのターンを意識してドラッグをかけた。すると大きなアタリがやってきた。なんだこりゃ、ヒカリじゃないな。妙な引きをする。水面下に走る魚体が見えた。あれ?一荷だよ。掛った二尾が好き勝手に暴れている。こういうことはたまにあることだが、ほとんどの場合掛っている一尾は逃げおおせる。なんとか二尾とも獲りたいよな~と丁寧に寄せていると、結局二尾ともバレテしまった。やり取りが慎重すぎたか。なんだかな、もったいない。
気を取り直して再開するが、風は強さを増すばかりであった。


うららかな日和であれば、更に面白い展開になりそうな、そのような雰囲気になったところで、苦戦が始まった。キャストする隙が無い程に、風が吹き止まなくなった。絶好のチャンスは泡と消えた。暫く頑張ってみてやっとの一尾。これで潔くロッドを畳む決心がついた。まだまだ日は高く、澄んだ水はキラキラに輝いていた。川に立つだけで、ホント気持ち良かった。




この日のキャンプ飯。土手には早くも菜の花が出始めていた。ありがたく一握り摘んできた。ざっくりと刻んでオリーブオイルと塩を絡めてサラダに。河原で摘んだフキノトウはバッケ味噌と豚肉の香草焼きに。バッケ味噌を焼き上がった肉でくるんで食した。
さて4月に入ってすぐのコト。毎週川に立っていると、訪れるたびにめまぐるしく変化する季節感が楽しくなってくる。仙台の桜はすぐにでも満開する勢いで一気に咲き始め、三陸でもちらりほらりと花開いていた。ここまで早く咲くというのは、ちょいと記憶に無い。しかし、気分の高揚とは裏腹に、またもや暴風にあたってしまった。なんだろうかね、ほんとツイていない。
川辺で風が止むのを待つが、一向にその気配なし。これではウェットフライも打ち込めない。仕方なしに昼寝を決め込んだ。
結局、日が沈み始めてようやく釣りが可能になった。随分と日が長くなった。おかげでイブニングの釣りができる。ドロッパーに#12パートリッジ&オレンジ、リードフライに♯16ブラックミッジを結んだ。背後から吹きつける風に乗せて、フライを流れに投じた。すると立て続けにヒカリが釣れてきた。




嬉しいヒカリ。鰭は透き通り、背鰭と尾鰭の先端は黒く染まっている。いずれももリードフライを捕えてきた。この後も釣れ続くのかと思いきや、アタリは続くことは無く、この日は少しばかり不完全燃焼気味で釣りを終えた。
翌日、朝飯前のひと時を、昨夕と同じ釣り方で探ってみた。

立派なヒカリが釣れてきた。ギラギラの銀の衣を纏い、凛としたその姿。春の使者、サクラマスの仔。これが釣りたかった。やっと見つけた春の探し物である。無事サクラマスになって、ここに帰ってくるんだよ。






陽の光を浴びて、背鰭や尾鰭の先端はしっかりと黒く染まり、胸鰭や腹鰭はヤマメの様な橙色は消え失せ、透き通ったガラス細工のようになっているのが良く分かる。いずれのヒカリもリードフライの♯16ブラックミッジを喰ってきた。
釣り開始から暫くの間はアタリが続き、のんびりと楽しめていた。日が高くなってくると風が強くなり始め、またもや釣りを中断せざるを得ない状況になった。それならばと、釣り場の移動も兼ねて、探し物の矛先はヒカリからコゴミへと向けられた。




すぐに目に入ったのは立派なスイセン。白や黄色、オレンジと。程無くしてお目当てのコゴミも発見。やはり今シーズンは芽吹きが相当に早い。




なんとワサビに菜の花、コゴミと役者が揃ってしまった。ありがたい春の恵み。風待ち、夕マヅメ待ち。こうなれば、のんびり、じっくりと食事にする。忙しく釣りばかりしていると、時間節約で食がおろそかになりがち。食事の準備は手間も時間もかかるけれど、本当はこういう時間をもっと大切にしたい。


軽く下茹で。茹で具合を確かめようと、三役者に出汁醤油をちょろりとかけて、ひと口で頬ばってみる。こりゃイケル!止まらなくなる。菜の花の辛味と苦みに続いて爽やかなワサビの香りと辛味が追いかけてくる感じ。噛むほどに引き立ってくる。コゴミのとろみがそれらを滑らかにまとめてくれて、どうにも後を引くのだ。気付けば危うく全部食べてしまうところだった。


ソッカイサーモンの燻製。良い香りにたまらずそのままひと口。これまたうまい!またまた止まらなくななってしまう。

茹でたパスタにサーモンと下茹でした三役者をあわせるだけ。出来上がり!白ワインでもあれば更に良かったな~。
日が傾き始めた頃、地元の延べ竿名人がやってきた。気付けば風は止み始めていた。私は竿を上げてのんびりしていたので、どうぞ遠慮なく釣って下さいと、名人の釣りを眺めていることにした。
釣り方は違えど、勉強になる。やはり狙いどころは同じ。流れの筋と付き場の石周りをトレースしている。すると水面に小さな波紋や飛沫が上がっているのが見えた。ヒカリのライズが始まったようだ。名人の仕掛けにアタリはある様にみえるが、なかなか掛らないらしい。
徐々に釣り下りながら探りを入れているが、次第にライズの数が多くなってきていた。暫くすると夕方5時を告げる町内放送が入った。それが合図のように、そろそろ毛鉤の時間だね~と、名人が川から上がってきた。
選手交代するかのように私が流れに入った。仕掛けは朝のまま…。






流れにフライを投じるとすぐにアタリが出る。掛らなかったり、掛ったり。テンポ良く釣れる感じは何年振りだろうか。ヒカリがたくさんいた頃を思い出す。


このような流れでライズを繰り返していた。釣っては放しを繰り返していると、ひと際良いアタリが来た。これはと思ったら、やはりヤマメ。しかももう一尾付いている。またまた一荷だよ!今回はバラすものかとさっさとやりとり、アユの友釣りよろしく吊るし込みで二尾とも取り込んだ。

同じ流れで釣れてきても、種として同じ魚であっても、ヤマメはヤマメ、ヒカリはヒカリなのである。よく釣れてくるフライパターンにも、その差が出てくることは十分に経験済み。この時期のヒカリは食用旺盛。水面近くのエサをぱくぱく良く食べる感じ。
川で生まれ育つヤマメ。その成長過程において、エサ取りや縄張り競争に負けるなどしてしまった個体は、ヤマメとして成熟が進まずに銀毛する。これが海へと下るヒカリになる。更には本州では遡上してくるサクラマスはほとんどがメスであるということも興味深い。
ヒカリはヤマメに比べてやせっぽち。故郷の川では育ちきらずに巣立ち、大海へ旅に出る。北の海を回遊の後見違える大きさに成長、サクラマスとなって生まれ故郷の川へ帰ってくる。サクラマスという魚の生き方は、山と海の恵みを繋ぐ営みそのものなのだと思えてくる。その生き様をもっと知りたい、だから釣りをする、ますますもってそう感じてしまうのである。
ヒカリに山菜、あれもこれも、大切な春の探し物。ヒトと自然のあり方を思うにつけ、いつもの春が訪れていることに安堵したり、嬉しくなったり。大自然に感謝です。ありがとう!
一日も早く、この禍が治まり、健やかな世の中になりますように。
THE ESSENCE OF FLY FISHING & THE ESSAY ON FLY FISHING vol.109/ T.TAKEDA
← 前記事 vol.108 目次 次記事 vol.110 →