エッセンス オブ フライ フィッシング & エッセイ オン フライ フィッシング vol.147 未踏の源流、一片の手掛かり/竹田 正
2024年08月09日(金)
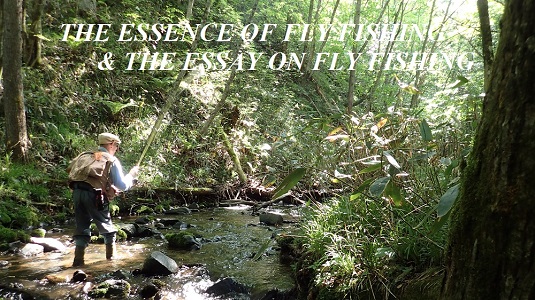
[vol.146]の続き……。
いざ退渓を始めると、沢筋には倒木が横たわるばかりで、それらは実に厄介だった。ここまで釣り上がってきたのだから、それは既に分かっていたこと。とは言え、落ち枝も多く常に脚に絡みつく始末で、これらがどうにも鬱陶しく感じられるのだった。
そのような時だった。草木の藪に一線の筋が見て取れたのである。それはシカやカモシカが付けた、いわゆる獣道だった。これこそ勿怪の幸いと、躊躇することなく、これに乗ることにした。言うなれば獣が整地したバイパス道路、直感した通り、脚に絡むものは断然少なかった。せいぜい数10cm程の幅であるが、足元の地面は踏み固められおり、これらを足裏の感触と目視で捉えることが出来るのであった。
暫くはこの獣道を使いながら順調に、快適に渓を下っていた。しかし、獣道は徐々に渓から離れ始めていた。そのことに気付いた時にはすでに、釣り上がって来た流れは眼下へと見る間に遠ざかっていたのである。
「ありゃ?川通しのほうがマシだったか?ルートを取り直すなら、すぐに戻れる今のウチか?」
そう思いながらも、歩きながらあれやこれやと考えることわずか数分、下っていたはずが上りになっていた。それでも立ち止まることすらせず、馬鹿なことに、まだ自分がシカにでもなったつもりで、勝手な都合を脳裏に並べ立てるのだった。引き返すことが面倒に感じられ、希望的観測が働いていたのだ。
「引き返してやり直そうと思えば、まだ戻れる。それにシカだって、喉は乾くだろう。いずれは水場に降りるはず、このまま山の頂上に出るはずもない……」
実際のところ、釣り上がってくる際に困難な岩場の落差などは無かった。あえて言うならそれは倒木だった。初めて入渓した沢となれば、川通しで戻るのが確実な方法であり、あの面倒に感じていたタイミングで「たまたま獣道に出くわし、楽なルートを選んだ」に過ぎなかったのだ。
思えば、良くも悪くも、それは直感であった。踏み固められた足場を頼りに、幾つもの藪を突破していくうち、獣道は急に下り始めた。遥か下に見下ろす感じだった沢が、見る間に視界に入り始めた。それは、もやもやと感じていた不安が過ぎ去り、ほっと胸を撫で下ろした瞬間だった。
「やれやれ……、ま、良しとするか」
少々スリリングな時間を味わうことになってしまったが、無事に本流筋へと戻ってきた。獣道のお陰で余計な疲労感を感じることなく、僅か30分足らずで枝沢を下ることができたのである。本流筋に戻ればルートを林道にとり、後は楽な下り。難なく車止めに帰着したのだった。
今回は、たまたま運が良かっただけのことである。途中で引き返し、川通しのルートに変更とならずに済んだのは幸いだった。足場の悪い急斜面の沢を下りてくる際は転倒しやすくあり、また、釣り上りよりも短時間で体力を消耗する。その為、沢を下るということは相当に気を遣うのである。
帰着後、装備の片付けを終え、ほっと一息。冷えたビールで喉を潤しながら、そろそろ晩飯の準備に手を付けようとしていた時のコト。
「ポツ、ポツ…、バラバラバラ……」
「ん。ありゃ?来んのかな?」と思うや否や、いきなりザーッと夕立がやってきた。乾かそうと広げていたものを、慌てて退避させるのだった。
あと少し、僅か15分くらい。もしも退渓が遅れていたとしたら、びしょ濡れになり「む~」と口をへの字に曲げながら帰着する羽目になっていたのである。
そろそろ突然の雷雨に見舞われやすい季節となる。森にいると空が見えないことも多々あり、増して釣りをしていると、どうしたって下を見てばかりとなるだろう。そのため急激に発達する雨雲には気付きにくいものである。風の流れや匂い、沢水、雷鳴など、これらの変化には注意しておきたいのである。

緑に映える白いエゴノキの花。咲き誇る花を目にすると、いよいよ夏のイワナ釣りも本番!という気分になる。その落ち花を目にしてしまうと、もはやこの季節まで来てしまったのか……、となる。時は瞬く間に過ぎ去っていくことに気付かされる。
晩飯を食いながら、一日の出来事を反芻していた。思いがけず遭遇した整列型白斑を持つイワナたち……。撮影してきた画像を眺めているうち、その血筋の濃さはどの程度なのか、それが気になり始めた。これまでの経験から、上流に行けば行くほど、それは高まっていくものと考えているのである。
思い起こせば、退渓時に眺めた上流の景色は、まだ釣り上りが可能な渓相に見えていたのだ。そこで地形図を取り出し、この日の記憶と照らし合わせてみた。地図上では、退渓した地点からその先約2~300m位は十分に、釣り上がりが可能と思える地形だった。
「未踏区間の釣り上がりに要する時間は2時間程度。何かと手間が多くかかるとしても、せいぜい3時間少々だろう……」
恐らくは、そこまで釣りきれば釣り上がりは限界に達し、この沢の探釣はひとまず終了となる。仮に今日の退渓点から再度入渓するとして、全行程の所要時間は往復で約6時間の見込みとなった。
その一方で、この日入渓した支流のみならず、これより以遠となる上流域にも、探釣したい未踏の沢が3本残されていた。行ってみなければ分からないことだが、これらの他にも有望な沢が幾つかありそうな雰囲気が、地形図から読み取れていた。これら数本の沢を全て調べ上げるとすれば、10日程を要するのは確実に思えた。
「さて、どうする。今日の枝沢を完璧に調べきるか、端から順に行くか、それとも可能な限り広範囲にアタリを付けてみるべきか……」
この日の結果を鑑みれば、どこもかしこも目が離せない状況になっていた。今すぐにでも核心に迫りたい気持ちも強くなり、ひと思いに最上流の沢へ入りたいという欲望が湧き出てきた。しかし、今日の出来事はジグソーパズルの貴重な一片と同様にも思えたのだ。
「これを基に次の一手を探し当てるのが妥当か。全容を知るには、まだまだピースが足りない。やるならやはり、足元から、順に。これだろう。明日はもうひとつ上流の沢なのかなあ……」
思いは浮かんだり沈んだり。酔いの気分に乗せて想像を巡らせながらシュラフに潜り込んだのだった。

翌朝、この日もスカッと青空だった。気分も上々。朝飯もしっかりと食った。里では真夏日となる予報が出ていたが、渓は前日同様に涼しいものだった。
森に日が差す頃を見計らって林道を上がっていくと、頭上からはオオルリ、沢筋からはミソサザイ、それぞれのさえずりが聞こえてくるのだった。響き渡る鳥たちの共演を耳で楽しむ一方で、サンショウの木を見つけては、その実と柔らかい葉をひと摘みしていく。するとその度に、辺りには爽快な香りが漂うのだった。時々、手の内にある実と葉を口に放り込み、嚙みしだく。瞬時に広がる刺激的な味と香りを楽しみつつ、目的の支流へ向けてつらつらと歩き続けた。
休みなく歩くこと1時間弱で目的の支流と本流筋の出合に辿り着いた。支流の入口は両岸が迫る様な地形であったが、藪に阻まれるようなことはなく、すんなりと入渓することができた。
周囲の状況を観察しながら小休止、それと共に釣り上りの準備を整えた。ロッドを繋ぎフライを結べば、今日も探釣の開始である――。



釣り上がりを開始。直後よりイワナはフライに喰いついてきた。あろうことか、立て続けに2尾をバラシてしまった。確実にキャッチしていかなければ調査にならない。気を引き締める。3尾め、白斑が少なめで良い雰囲気のイワナがやってきた。この沢でも整列型白斑を持つイワナの出現に期待が高まった。


掛ったイワナはヒラキに被さる枝に突っ込んでいった。ぐるぐるに絡んだティペットを解いてイワナを救い出す感じ。こうなると、イワナには何だか申し訳ない気持ちになる。


この枝沢、前日に入渓した沢よりも更に細流だった。逞しく生きているイワナたち。愛おしくなる。

このイワナの白斑は大きめ。

こちらは小さめ且つ少なめ。





小渓なりの懐の奥深さを味わいながら釣り上って行く。白斑は少なめで良い感じ。右体側を見ると整列型の要素を感じる個体。

このイワナは、この辺りでは良く見かける、言わば標準的な白斑という感じ。


淵とも呼べないような小さな淵で出会ったイワナ。このイワナも標準的な白斑。


このイワナも良く見かける標準型白斑という感じ。





赤みの強いイワナ。白斑の大きさはまずまずなのだが、整列はしていない。

白斑は小さめ。整列の要素は無し。整列型がなかなか現れない。






白斑の雰囲気は良いのだが、整列の要素は感じられない。標高が上がるとともに、狭かった谷は徐々に広がりを見せるようになってきた。


白斑はかなり小さい。水玉というよりも粒々のイメージ。

そうこうしていると、突如現れた。極僅かに小白斑が混在するが整列型とする。




小白斑が混在するが整列型の血筋を感じる。


倒木が流れを遮り、小さな堰になっていた。その落ち込みから現れたイワナ。どちらかと言えば白斑はランダムな配置で少なめ。


倒木の堰の上を狙うと、ここにもイワナがいた。堰を上がって鈎掛かりしているイワナを迎えに行く。腹鰭から尾丙にかけては整列している。この後暫くすると、ただでさえ多かった落ち枝が流れの上にも積み重なってくるようになり、釣り上りは限界を迎えたのだった。
さて。
これ以下、2日間に亘る今回の調査結果である。
・今回訪れた2本の沢について、いずれの沢にも整列型白斑を持つイワナが生息していた。
・初日に入渓した沢(分かりやすくする為、今後これを、シロウ沢と呼称する)では記録撮影できたイワナの総数は22個体だった。その内「整列型を2尾、準整列型は6尾」確認した。翌日に入渓した沢(今後これを、ヨシナ沢と呼称する)では総数25個体を記録撮影した。その内「整列型を1尾」確認した。
現時点では、「整列型」と「準整列型」を区別する明確な基準を見つけられていないため、これまで同様にあくまで視覚による判定である。
・シロウ沢とヨシナ沢について、整列型白斑が出現した個体数や白斑の状態を確認比較したところ、現時点では、白斑が少なく大きめの個体は、シロウ沢に多く見受けられる傾向があった。
・半数以上のイワナを取りこぼしてしまったため、整列型白斑の出現頻度は両沢共に不確定である。
・別件であるが、オビカゲロウについては、整列型との遭遇により釣りに注力したため、その生息が見込まれる幾つかの湧水を見つけたのみで、具体的な調査まで至らなかった。
以上である。
さて、さて。これまでにあちらこちらの沢で「整列する白斑を持つイワナ」を探し続けてきた。整列する白斑のイワナと初めて遭遇した件の沢のみならず、他所の源流にも可能性を見出すべく調査を続けてきた、その甲斐があったと実感している。
新たに調査した2本の沢でその存在を確かめることができた。この結果を踏まえると、今まで探してきたのはピースだったのだと、今更ながら気付かされた。点と点が繋がり結ばれて線となり、やがてそれらが面となって姿を現す時まで、個性的な白斑を求めて今後も調査を続けていこうと思う。
ところで、今回の釣行を経て感じたことをもうひとつ。これからは「整列型のイワナのみ棲む沢」を求めて訪ね歩くようになる、そのように思えてならない。幸運にも、その沢を見つけた時にはこの上ない喜びを感じつつも、このナラティブが終わりを迎えてしまうのかな、と想像してしまい、少し名残惜しいような気分にもなった……。翻って、イワナやフライフィッシングには興味の尽きるはずもなく、川旅には何かしらの物語が幾らでも生まれるのだろう、とも思えたのである。
この2日間の渓歩きでも、イワナを育むには豊かな森が大切であると、肌で感じとることができた。イワナたちは皆、食べ盛りであった。昨今の水不足と水温の上昇が気になるところであるが、イワナたちには無事に秋を迎えてたくさんの子孫を残して欲しいと願う。
釣りはロマン、謎解きに宝探し。イワナ探しの川旅はこれからも続く。整列型白斑を纏うイワナたちと出会えた悦び、大きな達成感を味わえたことに感謝!ありがとう!
THE ESSENCE OF FLY FISHING & THE ESSAY ON FLY FISHING vol.147/ T.TAKEDA
← 前記事 vol.146 目次 次記事 vol.148 →









